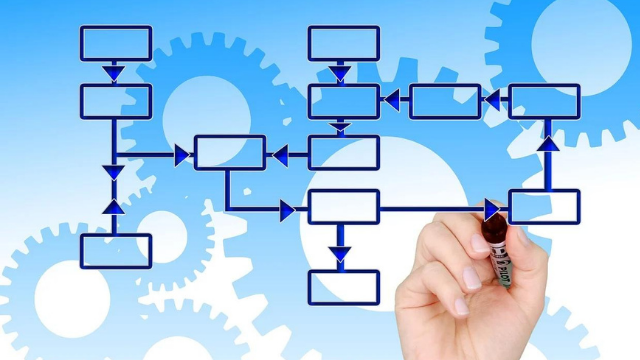SAP導入における失敗とは
失敗のパターンはそれほど多くはないため、まずはどのような状態をプロジェクトの失敗と呼ぶのか理解しておく必要があります。SAP導入における失敗としては次の3つがあります。
SAP導入における失敗要因
(1)システムがそもそも稼働しない
(2)導入におけるコスト面、スケジュール面が大幅にオーバーする
(3)システム導入の目的が果たせない
システムがそもそも稼働しない
先方都合などによりシステムを導入したものの結局稼働しないケースや、そもそも導入前に現場の反対などが要因で頓挫するケースもあります。もちろん先方都合でやむなく打ち切りになることもありますが、事前に綿密なコミュニケーションを経ておくことで一定防げるものなので、丁寧なすり合わせが求められます。
導入におけるコスト面、スケジュール面が大幅にオーバーする
コンサルタントであればプロジェクト開始時にWBSを作成して、その通りにスケジュール管理をすることになるかと思いますが、SAPでは通常のプロジェクト以上にバッファーを取っておく必要があります。
例えばSAPなどの基幹システム系のプロジェクトでは下記のような遅延要因が存在します。
- 要件定義のスコープ漏れ
- テスト段階で本番業務に即していないシナリオを試してしまう
- 運用段階で他部署の巻き込みに失敗する
SAPに限らず大規模なプロジェクトでは予期しないインシデントが数多く発生することを念頭にスケジュールを作成することが推奨されます。
システム導入の目的が果たせない
DX化の流れのなか、トップダウンでSAP導入だけが決まってしまい、導入したものの現場に使われないシステムになってしまうケースもあります。あくまでSAP導入はDX化、効率化のための手段であり、それ自体が目的ではないということをクライアントとしっかり会話しておくことが必要です。
ERP導入が失敗する要因を事例とあわせて紹介
導入後のコストを意識出来ていない
1つ目はクライアント側が導入後のコストを認識出来ていないケースです。SAPは導入して完結する売り切り型ではなく、保守としてコンサルタントが継続して参画することが一般的です。
導入費用も大きな出費となりますが、その後の継続した保守費用もクライアント企業にとっては大きな負担となります。導入後についても事前にクライアント企業の担当者としっかりと認識を合わせておく必要があります。
給湯器の大手メーカー、ノーリツは2000年12月期の決算において16億円の特別損失をシステムの廃棄により計上しています。この時のノーリツの連結売上高が1402億円なので、その1%を超える16億円というのは莫大な損失です。ノーリツが4年がかりで進めたSAPパッケージは完成していたにも関わらず、高額な保守費用によって破棄されています。
「システムは外付けのシステムも含めていったん完成していた。にもかかわらず廃棄を決めた理由は、メーカー製パッケージを採用したがゆえの高額な保守費用の発生にあった。数年ごとにバージョンアップに迫られ、外付けしたソフトの動作確認や改修作業が発生してしまう。そして数億円の保守費用が発生することに気づいたのだ。」
(参考:【事例】ERP廃棄で16億円の特損—ノーリツ)
システム導入が手段ではなく、目的となっている
2つ目のケースはシステム導入が手段ではなく、目的となっているケースです。経営陣がDX化の名のもとトップダウンで無理なシステム導入を行うケースもあります。
システム導入が目的化してしまうと、導入したものの業務に即していないため、現場で使用されることのないシステムになってしまいます。
全社的な取り組みとなっておらず、部署間でコミュニケーションが取れていない
3つ目はSAP導入が全社的な取り組みになっておらず、部署間の連携が取れていないパターンです。基本的にSAPをはじめとする基幹システム系のプロジェクトは製品の生産から販売、納品、請求書発行など全体を担うため全社横断的なものになることが一般的です。
その際に部署間の連携が取れていないと、一部の部署のみで使われる単なるシステム導入になってしまうことに注意が必要です。
システム要件と実際の業務要件のすり合わせが出来ていない
4つ目のケースはシステム要件と実際の業務要件のすり合わせが出来ていないパターンです。要件のすり合わせが不十分だと、SAP導入後に現場の業務に即していないという理由で、手戻りが発生し、最悪の場合システム破棄となります。
SAPの事例ではないですが、アクセンチュアは物流管理システム導入の際にクライアント企業であるテルモから賠償を求められています。
「医療機器大手のテルモが物流管理システムの刷新に失敗。構築プロジェクトは中止に追い込まれた。テルモは開発委託先のアクセンチュアを相手取り、38億円の損害賠償を求めて提訴した。」
(参考:物流管理システム刷新に失敗 38億円の賠償求めベンダー提訴)
このように大手のコンサルティングファームでも業務のすり合わせが不十分なままシステム導入が進んでいるケースが散見されるため、ERP系のプロジェクトに参画する際は一層注意が必要です。
導入後の見直しが出来ていない
最後に導入後の見直しは必須です。導入自体はゴールではなく、そこをスタートとしてクライアントの業務を効率化できているのか逐次チェックする姿勢が大事です。この姿勢でプロジェクトに臨めばクライアント企業との良好な関係も構築できます。
ERP導入において失敗しないためのポイント
費用対効果を算出し、適切な導入を行う
SAPは基幹システムであり、企業の基盤となるものです。導入時には多大なコストがかかるため、少しでもコストを軽減する方向に議論が移りがちですが、費用をカットすることは機能をそぎ落とすことを意味します。
絶対に一元化すべき部分などは事前にしっかり握っておくことで、無駄なシステムの併用も避けることが可能ですし、逆に非常に高額な費用がかかることも避けることが出来ます。
ERP導入後の運用について、事前に議論をしておく
導入後の保守費用が高く、システム自体を廃棄したノーリツの例は先述しましたが、導入後の運用についても事前にクライアントと議論をしておく必要があります。
費用以外の例では、部署ごとの責任範囲やクライアントとコンサルタント側の業務の切り分けなどが挙げられます。あくまで導入自体が目的とならないように意識することが大事です。
実際の現場担当者もプロジェクトの一員として参画させる
システムを導入する際に実際の業務に即しておらず、現場が使ってくれなければ何の意味もありません。コンサルタント側は現場へのヒアリングなどを通して、現場の意見を完璧に取り入れた気になっていることがありますが、反映しきれていないことも多々あります。
SAPを導入する際は、実際の使用者となる現場担当者もプロジェクトの一員として参画させることで導入後に使われない可能性を軽減することが可能です。
既存のシステムとの連携性を考慮する
SAPは基幹システムであり、情報を一元化するものであるため、既存システムとの連携が不可欠です。既存システムをSAPですべて代替することは稀で、一部システムを残すケースも大いにありえます。
SAPを導入しても連携性のチェックが甘いと、一部は手動で業務を進めなければならないということにもなりかねません。そうなってはSAPの持つ効率性のメリットが十分に生かされないため、SAP導入の際は連携性を事前に確認することが求められます。

まとめ
今回の記事では、SAP導入の要件定義について事例とともに解説しました。コンサルティング案件などを探している方、事例を知りたい方は、ぜひfoRProまでご相談ください。